蒜山ジャージー農業協同組合
蒜山ジャージー農業協同組合(以下ジャージー農協)は、ジャージー種を主とした16軒の酪農家から成り、平成4年から現在まで、3ヶ所の乳業メーカーにジャージー乳及びホルスタイン乳を出荷しているアウトサイダーである。
ジャージー農協の16軒はいずれも家族経営で、平均搾乳頭数は40頭である。
ジャージーは、最初ニュージーランドから輸入しており、年間乳量4000kg程度だったが、アメリカから輸入するようになってから大型化した。
現在では年間乳量 8000kgを超えるという。
今回は、ジャージー牛飼養や、アウトサイダーになったきっかけ等について、代表理事組合長・楢本氏、第一理事・遠藤氏にお話を聞かせていただいた。

ジャージー牛導入の経緯〜国の草地拡大事業〜
昭和27年、蒜山地区酪農振興計画が立てられ、それまでほとんど乳牛が導入されたことのなかった蒜山地区において、草地の拡大や乳牛の導入が図られた。
>
昭和30年には、国の高度集約酪農振興施策に基づき、蒜山地区が集約酪農の地域指定を受けたことにより、初めてジャージー牛が導入された。
この事業に乗って、ジャージー牛を飼い始めた農家は100軒以上あったという。
しかし当時はジャージー乳は消費者に受け入れられず、やめていく農家も多かった。
この時、蒜山地区のうち八束村と川上村の酪農家によって、蒜山酪農農協(以下蒜酪)を設立、昭和41年から県酪連との取引を始める。
蒜酪は、独自の乳業プラントをもち、生乳を加工、販売し、乳業者としての事業を行う組合であり、生乳の委託販売(流通)は行っていない。
ジャージー再生産奨励金をめぐる不平等〜蒜酪組合員の奨励金独占〜
県酪連は、ホクラク農協から販売委託を受けて、蒜山地区のジャージー乳の販売を行っており、
その9割は蒜酪に、1 割は大阪黒川乳業に販売されてきたが、黒川乳業への販売価格がkg単価133円〜135円であるのに対し、
蒜酪へは110円〜118円で販売していた(平成4年度の両者の価格差25円)。
蒜酪は、県酪連からこのような優遇措置を受け、これによって得た利益を、組合員に対してのみ、
ジャージー再生産奨励金という名目で還元してきた。
当時、県酪連の集乳量、販売量におけるホクラク農協の割合は50%を占め、歴史も県酪連より古く、
ジャージー振興地区を抱えるホクラク農協の県酪連に対する発言力は強力であり、また、ホクラク農協内部において、
蒜酪がジャージー乳について圧倒的なシェアを占めていたことから、蒜酪のホクラク農協に対する発言力は相当に強かった。
そのような力関係の中で、ジャージー再生産奨励金制度が生まれたわけだが、同じように県酪連に販売委託している、
蒜酪組合員でない蒜山地区のジャージー農家の間には不平等感が高まっていた。
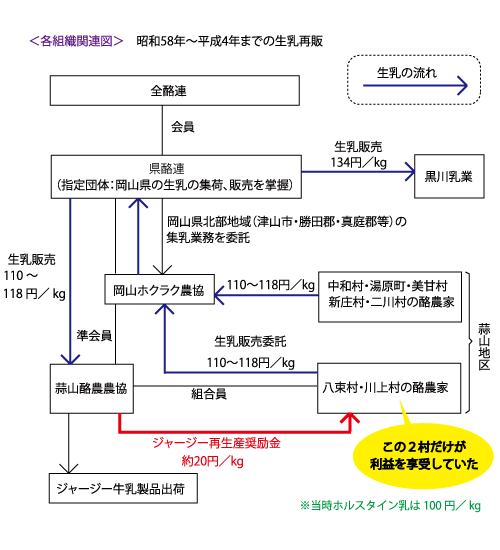
ジャージー再生産奨励金の内訳
1.分別ジャージー乳生産の組合員に対して20円/kg
2.上記 1 以上に利益のあった場合、混合乳の組合員に対して3.4円/kg
3.上記1と2の合計額以上に利益のあった場合、同割合で追加払い。
4.ジャージーの飼育頭数を増頭した組合員に対して増頭奨励金として4万円/頭
備考
※平成14年4月1日:岡山ホクラク農協・旭東酪農業協同組合・水島酪農業協同組合・瀬戸内酪農業
協同組合が合併→おかやま酪農を設立、合併前各組合の権利義務一切を承継
※平成15年9月30日:県酪連解散→おかやま酪農が権利義務一切を承継
混合乳をめぐる軋轢〜ジャージー乳100%農家の奨励金独占〜
また、この奨励金は、蒜酪の中でもジャージー牛のみ飼育している農家にだけ利益配分され、
ジャージー牛とホルスタイン牛の混成の農家には一切配分支給されなかったため、ジャージー専門農家と混種農家との間の軋轢を生んだ。
これを解消するため、当時蒜酪の組合員だった美甘氏(のちのジャージー農協組合長)は、平成3年度、当時の蒜酪組合長の要請を受けて、
ジャージーとホルスタインの混合乳の有利販売を進めた。
平成4年には、大山乳業から前向きに検討するとの回答を得ることが出来たにもかかわらず、蒜酪は突然、混合乳の有利販売を否定する発言をした。
県酪連の会長に至っては、混合乳をやるならアウトでやればよいなどと発言したため、大山乳業との交渉は白紙となり、
事実上アウトサイダーでなければ混合乳の有利販売は出来ない状況となった。
蒜酪組合員以外の育成牧場利用を制限〜公共育成牧場の利用独占〜
さらに、蒜酪は、八束村からの委託を受けて管理運営している公共育成牧場について、蒜酪の組合員以外の利用を制限したため、 蒜酪以外のジャージー飼育農家にとっては、厳しい状況が続き、廃業に追い込まれる農家もあった。
アウトサイダーへ〜決断、新たな出発〜
蒜酪以外のジャージー農家は経営破綻に追い込まれる。
「このままでは食べていけない、年を越せない」となった農家の選択は…
このような一連の蒜酪・県酪連のやり方に対して異を唱える6軒の酪農家が蒜酪内、蒜酪外から集まり、アウトに出る準備を進めた。
販売先については、蒜酪から孤立した美甘氏と、県酪の販売担当だった土居氏が営業に東奔西走し、
県酪連からの度々の圧力(原乳供給を武器にしての乳業への脅し)にも屈せず、春日牧場(岡崎乳業と合併し現在春日乳業)、
六甲牧場等との契約が成立した。
これを受けて平成4年11月、美甘氏が組合長となって、農事組合法人蒜山高原牛乳生産組合を設立し、
アウトサイダーとしての生乳出荷に踏み切った。
当初は、無事にローリーを送り出すまではおちおち眠れず、緊張の日々だったという。
すでに廃棄処分となった6トンローリーを秘密裏に入手し、よく洗浄し使えるように仕上げた。
季節外れの大雨の晩、アウト初出荷を決行する。
夜中に集乳を開始、夜明け前に大阪の黒川乳業に向け走った。
昼前に黒川乳業に到着し受乳を依頼したが、すでにホクラクから連絡が回って受乳を拒否されてしまった。
大雨の降りしきる中、生乳を積んだ6トン車は神戸に向かった。
今回のアウトを計画し実行した美甘組合長は黒川乳業の受乳拒否も考えの中にはいっていたのだろう。
もしものために神戸の六甲牧場に手を打っておいたのだ。
六甲牧場に着いて、受乳係りに「事の経過」を説明すると上司に聞いてくるという、「もうあとが無い」と思った美甘組合長は、
受乳係りが帰ってくるまでの間に受乳ホースをつなぎ、コックを開いてしまった。 白い牛乳がドッと流れ受乳室に入った。
ともかく第1便は乳業に収めることができた。 そして第2便、第3便と続く。
これに対し蒜酪は、アウトサイダーとなった組合員農家へのジャージー乳再生産奨励金の支給停止、公共育成牧場の利用拒否、
蒜酪の事業の一つである受精卵移植利用の拒否、乳牛の登録料を通常の2倍に設定する、前渡金の貸し出しの拒否等を内容とする通知を出した。
組織との闘い〜蒜酪を独禁法などで告訴〜
平成7年にはホクラク農協から脱退し、平成8年、農事組合法人蒜山高原牛乳生産組合から蒜山ジャージー農業協同組合となり、
食生活の変化からジャージー乳が注目されたこともあって、参加農家も増えていった。
この年、蒜酪の独占禁止法違反、公序良俗違反、県酪連の委託契約違反等と、それに伴う損害賠償責任を求めて裁判を起こし、
平成16年までの約7年間かけて争ったが、公共育成牧場の利用以外の項目についてはいずれも棄却されるという結果となった。
しかし現在のジャージー農協組合長である楢本氏は、このような裁判を起こすこと自体が、
アウトサイダーに対する不当な圧力を抑止する効果をもたらすと言う。
楢本氏は、落合地区のジャージー飼養農家である。蒜山地区以外の農家を取り込んだことで、ジャージー農協の存在感は格段に増したという。
現在蒜酪以外のジャージー農家は、全てアウトサイダーである。
蒜酪以外のジャージー農家は、辞めるかアウトになるか、どちらかしか生き残る術はなかった。
アウトサイダーになって、ジャージー乳価を設け、ホルスタイン乳と価格差をつけた。
売上の5.5%は、組合費として徴収している。
これまでは、8割以上ジャージー種であればジャージー乳として売れたのだが、
平成16年7月から、全てジャージー種でなければジャージー乳としては売れなくなったため、
現在残っている少数のホルスタインの、ジャージーへの切り替えを進めている。
闘いは続く〜アウトサイダーとは?〜
平成4年にアウトに出てから、今日までの道のりは決して平坦ではなかった。
血乳や、異物混入により、生乳を廃棄処分したこともあった。
原因が特定できた場合は、その農家が廃棄分の損害を負担し、特定できなかった場合は、組合員全員で負担した。
乳質についても課題が残っており、仲間を増やすため、無理をして勧誘した結果、組合員の質を下げることになってしまったのではないか、
と、楢本氏は振り返る。

確かに、アウトサイダーとして最初に飛び出した6軒の農家の味わった辛酸を思えば、
後に加入した農家との間の、アウトであることに対する温度差は否めない。
年月が経つにつれて、当初抱いていた闘争心や、信念、理念といったものが薄れていくと、
アウトサイダーとしての存在自体が揺らぐことになるだろう。
組合という形態をとっている以上、リーダー的役割をする人物が必要なのはもちろんだが、
組合員全員が役員のような心構えでいることが、アウトサイダーには求められる、と、楢本氏、遠藤氏は口を揃える。
なぜならば、自らの手で販路を切り開くのがアウトサイダーであり、そこへ送り出す生乳には責任を持つことが求められるからである。
しかしそれは、一生産者として当たり前のことであり、その当たり前の意識さえも持たずに済むような既存の組織形態には疑問を感じざるを得ない。
〒372-0014 群馬県伊勢崎市昭和町3928
TEL 027-050-8220 FAX 027-050-8221 e-mail: [email protected]
copyright (c) Milk Market Japan. All right reserved.
